鉄道唱歌 山陽・九州編の歌詞(西広島・五日市・宮島)や観光・歴史について、わかりやすく解説してゆきます!
まずは原文から!
いつしか過すぎて嚴島
鳥居を前にながめやる
宮嶋驛につきにけり
さらに読みやすく!
いつしか過すぎて 厳島
鳥居を前に ながめやる
宮島駅に つきにけり
さあ、歌ってみよう!
♪いつしかすぎてー いつくしまー
♪とりいをまーえに ながめやるー
♪みやじまえきにー つきにけりー
神戸駅→兵庫駅→鷹取駅→須磨駅→舞子駅→明石駅→加古川駅→姫路駅→相生駅(旧・那波駅)→岡山駅→倉敷駅→福山駅→尾道駅→糸崎駅→三原駅→海田市駅→広島駅→西広島駅(旧・己斐駅)→五日市駅→宮島口駅→岩国駅→柳井駅→徳山駅→防府駅(旧・三田尻駅)
※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ表記
※鉄道唱歌のできた当時(1900年)は、防府駅(旧・三田尻駅)から先は開通していなかったため、徳山港から船で門司(九州)へ
広島駅からは、西広島・五日市・宮島方面へ
「己斐の松原」とは?

太田川放水路・己斐地域をゆく(横川~西広島間)
己斐の松原とは、現在の西広島駅(広島市西区)周辺にあったとされる松原のことをいいます。
現代では、この辺りに松原は存在しません。
西広島駅は、当初は「己斐駅」だった
また、西広島駅は明治時代の開業当初は「己斐駅」という名前でした。

西広島駅(旧・己斐駅)(広島県広島市西区)
「カープ」の由来にもなった己斐(こい)
己斐とは、カープ(鯉)の語源となった言葉でもあります。
- 己斐→鯉
となり、広島城は「鯉城」という別名で呼ばれていました。
この「鯉城」から、鯉→Carpとなり、広島東洋カープの名前の由来になっています。
アストラムラインとの合流駅・新白島駅 (広島→五日市)
広島駅を出ると、新白島駅(広島市中区)というアストラムラインと交差する駅に着きます。
ここから広島市街地中心部の「本通り」まで行けるため、便利です。
もちろん、
- 本通り
- 紙屋町
- 八丁堀
方面へは、路面電車で広島駅からも行けます。
アストラムラインとは?
アストラムラインとは、1994年に開通したトラム式の鉄道列車です。
トラム式は、富山でもみられる方式の鉄道です。
アストラムラインは、1991年に歩道橋が落下するという悲惨な事故が起きており、工事のミスが指摘されています。
横川駅(広島市西区) (広島→五日市)
横川駅(広島市西区)は、可部線との分岐点となっています。
(当たり前ですが)群馬県の横川駅とは異なり、また読み方も異なるため、注意しましょう。
- 広島県→よこ「が」わ
- 群馬県→よこ「か」わ
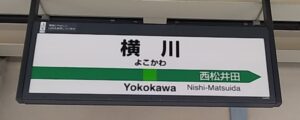
横川駅(群馬県安中市)
ちなみに、群馬県の横川駅は、軽井沢方面へ続く碓氷峠の険しい急な坂道を克服するため、明治時代に「アプト式」という方式を採用した線路として知られます。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

横川駅から出ている、可部線
可部線はかつて、日本海側の
- 島根県浜田市
までを結ぶ、陰陽連絡路線の役割を担う路線として、建設計画がなされました。
途中の「三段峡駅」までで廃止
しかし実際には戦争中に建設が断念され、途中の三段峡駅までの建設となりました。
つまり、かつては
- 横川駅~可部駅~三段峡駅
までの営業だったわけです。
2003年、可部~三段峡までの区間が廃止
その三段峡駅までの区間も、途中の可部駅までの区間を残して、2003年に廃止となってしまいました。
つまり、
- 横川駅~可部駅
までの営業に、変更に変更されたわけです。
これは沿線の人口減少や、1960年代以降のモータリゼーションなどに勝てなかったことなどが挙げられます。
自動車が普及して高速道路が充実してくると、無理に線路を建設しても利益が上がらなくなってくることは、容易に想像できたためですね。
2017年、「あき亀山駅」までの路線が復活
しかし、2017年には可部駅から
- あき亀山駅(広島市安佐北区)
までの区間が地域住民の要望により復活して、可部線の区間は
- 横川駅~可部駅~あき亀山駅
となっています。
西広島駅から先は、広電と並走 (横川→五日市)
西広島駅を境に、それまで市街地の道路を走る路面電車であった広島電鉄(通称・広電)は、ここで
- バラスト+枕木
の、通常の鉄道線路になります。
バラストとは、いわゆる線路にまく「じゃり(砂利)」のことをいいます。
枕木とは、線路と垂直に何枚も並べて敷く、あの板のことです。
ここで広電は、宮島までJR山陽本線と並行します。
しばらくして
- 新井口駅(広島市西区)
- 五日市駅(広島市佐伯区)
などを過ぎていきます。

新井口駅(広島県広島市西区井口)
広電を、JR山陽本線が勢いよく追い越してゆく
また、広島電鉄はJR線と比較して停車駅が多いため、ゆっくり走る広電を追い抜いていくJR山陽本線は、まるで特急列車や新幹線のように思えてしまいます。
広島市中心部へと直通する、広電
広島電鉄は地域住民の「近場の移動の需要を拾う」のがメインという性格もありますが、
- 八丁堀
- 紙屋町
など、JR線が通っていない広島市街地中心部から宮島へ発着できる強みもあります。
五日市駅(広島市佐伯区)に到着
やがて、五日市駅(広島市佐伯区)に着きます。
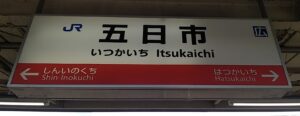
五日市駅(広島県広島市佐伯区)
「定期市」に由来する地名
この地域には、
- 「五日市」
- 「廿日市」
という、似たような地名が続きます。
これは、昔の市場というのは、何日か1回に開かれるのが当たり前だったことに由来します。
「五日市」では、どのように商売をしていた?
例えば「五日市」ならば5日に1回の売り出しを行い、「廿日市」ならば20日に1回のペースで売り出しを行います。
他にも、広島とは関係ありませんが「八日市」ならば、8日に1回です。
また、東北地方の馬市のように、春と秋の年2回という限定的な市場もあったようです。
「じゃあ、残りの店をやってない日はどうしてたの?」と思うかもしれません。
しかし、私も調べたけどよくわかりませんでした。
恐らく、この隙間の日には、農業と兼業していたのかもしれません。
また、昔は現代と違って、仕入れや品物の保管も大変だったのでした。
そのため、現代と違って毎日店を開けなかったのかもと思います。
しかし、貨幣経済が次第に発展してくると、商業をメインに生業とする人も増えてきたことでしょう。
「卸売業」などができれば、仕入れや輸送などのコストや手間がなくなるために、分業体制が進んでゆくことになります。
その結果として、お店はモノを売ることだけに専念できるようになります。
現代のように、コンビニのような便利すぎる店は存在しなかった
このように、昔はこの「五日市」「廿日市」などのように、店が開かれる日は限定的であったのでした。
そのため、消費者はそれに合わせて買い物にいかなければなりませんでした。
現代のようにコンビニが24時間365日オープンしているというのは、当時の常識からしたらむしろありえない話なのでした。
余談ですが、現代の日本はサービス過剰ともいわれ、これだけ便利な世の中です。
そのため、そのシワ寄せは必ず「労働者の長時間労働・重労働」という形で跳ね返ってきます。
また、コンビニの店員も常に人手不足であり、時給を高く設定しないと求人を出しても誰も面接に来てくれません。
そのため、時給も1,000円~1,200円など当たり前の世の中となりました。
その時給が上がった分は、商品の値段にシワ寄せされてきます。
そのため、昔は100円で買えたオニギリも、今や150円~180円ほどにまで値上げされています(もちろん、円安などによる輸入品原材料高騰の影響もあり)。
その他の「定期市由来」の地名
他にも、「五日市」「廿日市」などと同じような語源の街として、
- 三重県の四日市市や
- 福岡県の二日市
などがあります。
また、五日市という地名は、東京都の西部にある、あきる野市にもあった地名です。
それは
- 「五日市線」
- 「武蔵五日市駅」
という名称に残っています。
なお、武蔵五日市駅という駅名は、恐らく広島県の五日市駅と駅名が重複しないよう、旧国名「武蔵国」の「武蔵」を頭につけて、駅名重複を回避したのでしょう。
五日市を出て、宮島・廿日市市へ
やがて、
- 廿日市駅(広島県廿日市市)
- 宮内串戸駅(広島県廿日市市)
などを過ぎていくと、窓の左側には大きな宮島の景色が登場します。
宮島口駅(廿日市市)に到着(五日市→宮島口)
ほどなくして、宮島口駅(広島県廿日市市)に到着です。

宮島口駅(広島県廿日市市)

宮島口駅(広島県廿日市市)
廿日市市(はつかいちし)
広島県廿日市市には、速谷神社という、交通安全の神様を祀る神社が存在します。
また、宮島も、廿日市市に属する島です。
西国街道(山陽道)
かつて鉄道も無かった江戸時代以前は、この辺りは山陽道というふうに言われてました。山陽道は西国街道ともいわれます。
西国街道とは、京都の東寺を出発して九州に至る、徒歩または馬でゆく、昔の旅人が通った道のことです。
菅原道真公も通った、西国街道
かつて菅原道真公も、九州の大宰府へ左遷のときに、西国街道を通ったとのことです。
次は、船で宮島へ
次回は、宮島へ船で渡ります!

コメント